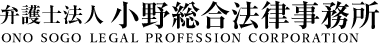2022/02/18 <遺留分>
代表社員 弁護士 庄 司 克 也
※小野総合通信 Vol.73(2021年秋号・2021年11月1日発行)より転載
1. 昨今,相続紛争予防のため遺言を作成する風潮が高まり,自筆証書遺言についても保管や様式を使い勝手の良いものとする法改正もされている。私は,遺言の作成が一般化することが,相続紛争を解決するツールとなるか懐疑的であった。すなわち,死後の紛争が前倒しになる…すなわち,生前にどれだけ自分に有利な遺言を書かせるかという紛争に変容するだけではないかと考えていた。しかし近頃寄せられるご相談は,遺言者が自らの意思と主体的判断で遺言の作成に臨まれるケースが多く,私の心配はいささか天邪鬼なものであったと反省している。
2. 遺言が一般化するのに伴い,遺留分という言葉も,遺言者の立場であれ,遺族の立場であれ,浸透してきたように思われる。そして,相続法の改正により令和元年7月1日以降に発生した相続については,遺留分制度の内容が一部変更された。今後は,改正後の遺留分制度による対応が求められるケースに置き換わっていくこととなる。
3. 遺留分は遺言が存在する場合に問題になる制度で,遺言がなければ遺留分の問題も生じない。私有財産制度等という大げさなことを持ち出すまでもなく,被相続人は,生前に自分の財産を自由に処分できるのが原則である(時折,本人が生前に自分の財産を費消するのを快く思わない法定相続人がおられるが,大きなお世話というほかはない。)。従って,自分の死後,遺産をどうするかも原則として自由に決められる。これが遺言である(主体的に何も決めなければ,…遺言を作成しなければ…法律の規定に従うことになる。)。
しかし,法はこの原則を修正し,被相続人の財産の一定割合の承継を一定の範囲の相続人に保障した。これが遺留分である。この保障割合を遺言による遺産分配で害された遺留分権利者は,その回復を求めることができるというわけである。その趣旨については「遺族の生活保障」とか「遺産の形成に貢献した遺族の潜在的な持分の精算」などと言わる。これらが一般的に認められる(であろう)一定範囲の者に遺留分が認められているのである(「事実としては」およそ生活に困ることのない裕福な者や遺産形成に全くと言っていいほど貢献をしていない者も含まれうると思うが,法律の規定としては一定の範囲の者を定型的に権利者として定めるほかはない。そのことに文句を言ってみても始まらない。)。
4. 遺留分権利者は配偶者と子と直系尊属(父母)である。
また,保障される割合は,前二者が母数となる被相続人の財産の2分の1,直系尊属は3分の1である。各人毎の保障額はこれに各人の法定相続割合を乗ずる。被相続人の兄弟姉妹には遺留分はない。
5. 遺留分は権利者がそれを行使して初めて具体的な権利として機能する。行使するかどうかは権利者の意思にかかっている。遺言者は「自分の意思を汲んで遺留分を行使することはない」と信じて遺言することも多いが,その期待は往々にして裏切られる。逆に遺言が不公平不合理なもので,どう見ても何らかの外的要因により作成されたと考えられるような場合,そのことをもって遺言無効とすることは難しいが,遺留分は必要最低限の公平(あるいは正義?)を実現するため最後の防衛線として機能する。
6. 遺留分を侵害する遺言とは,遺留分権利者に遺留分相当の財産の取得を認めない遺言である。「全財産を特定の相続人に相続させる」といったものが典型である。妻には不動産,子1には現金100を,子2には現金200をといった遺言の場合,遺留分を侵害する遺言かどうかは「計算」してみないとわからない。
侵害されているかどうかの計算について抽象的に正確に説明するには紙幅が足りないので,おおざっぱな説明をすると,「被相続人が相続開始時に現に有した財産の価格」に「贈与した財産の価格」を加算したものを母数とし,各権利者の遺留分割合を乗じて算出し,遺言による分配がこれに足りているかを比較する。「贈与した財産」を加えるのは,被相続人が,生前にその財産の大半を,特定の相続人や第三者に贈与した場合には,現に残っている遺産だけを母数とするのでは,容易に遺留分制度の趣旨を潜脱されてしまうからである。「自分に都合の良い遺言」を書かせようとまでする者にとって,生前から被相続人の財産処分を進める策を講ずることは常識であろう。ただ「贈与した財産」は時期等が限定されている。「法定相続人」への贈与は,相続開始前10年以内にしたものでかつ婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として受けたもの(いわゆる「特別受益」)に限られる(相続法改正前は,いつまでも過去に遡れたが,相続法改正により限度が設けられた。)。「アニキ(アネでもオトウトでもよい)は,新婚当時,オヤジから自宅購入資金をもらった」と言うのは,気持ちはわかるが遺留分算定の母数としては考慮されないこともある。相続人以外の者に対する贈与は,さらに短く相続開始前1年以内にされた贈与に限定される。なお贈与の当事者(被相続人と贈与を受けた者)が遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた贈与には時期の制限はない。
その他,やや複雑な計算を経て,遺留分が侵害されていることが判明した権利者はこれを侵害した者(遺言により財産をたくさん取得した者や贈与を受けた者)に対し遺留分侵害額請求を行う。これにより,侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができるというわけである。相続法改正前は,遺留分は侵害者が取得した財産そのものについて被侵害割合に応じた権利を回復する制度とされていたが,改正により,単純な金銭請求権とされた。権利の内容としては明瞭であるが,不動産や動産といった「財産自体」の権利回復を求めることはできなくなったので,相手方の資力いかんでは絵に描いた餅ということになりかねない。
7. 最後に,改正前は「遺留分減殺(ゲンサイ)請求」といういささか厳つい名称であったが,改正後は「遺留分侵害額請求」と称されることとなった。名称はスマートになったが,遺留分をめぐる諸々の紛争の背景にあるものまでスマートになるわけではない。