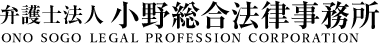2022/04/01 <司法制度改革をもう一度>
弁護士 26期 藤 村 啓
※小野総合通信 Vol.74(2022年冬号・2022年2月1日発行)より転載
1 現行民事訴訟法(平成10年1月1日施行)は,民事裁判に携わった裁判官,弁護士等の法律実務家が公正で迅速,適正な民事裁判を目指して積み重ねてきた裁判実務の経験と知恵の織り成す成果物であり,新たな民事裁判手続法の実践により,紛争の解決と法創造という国民の期待に応えるべく民事司法機能の更なる持続的発展が実現できるものと大いに期待された(「新しい民事訴訟法・規則の運用に関する懇談会」判例時報1616号,1617号,1623号,1624号,1626号及び1627号参照)。
ところが,施行から20年余が経過した今,当事者の立場で民事裁判に関わってみると,その運営は上記の役割を実践する民事裁判とは随分かけ離れている印象を受ける。裁判所においても,今更ながらの感があるが,民事裁判の機能改善のために争点整理の充実が喫緊の課題とされ,IT技術を導入する等してその検討が盛んであると聞く。しかし,この間,裁判官,弁護士ら法律実務家が怠けていたというわけでもないであろうから,一体何ゆえにこのような民事裁判運営となっているのか真剣に考えてみる必要があろう。
2 今日,裁判の現場では,多くの裁判官が,争点整理と称して主観的には実に真面目に当事者双方の主張の対立点を突合して一覧表化する作業に腐心し,これを終えると,争点整理が完了したとして,審理促進に追い立てられるように,集中証拠調べと称する証拠調べの集中期日を実施して審理を終え,和解を勧試し,不成立なら判決を下して,これをもって民事裁判の役割を果たすものと考えているようである。
しかし,このような裁判運営は,往々にして紛争の中核の把握があいまいとなり,争点(対立点)が多岐にわたり絞り切れていないまま,内容よりも時間制限が厳しく管理される中で,争点(対立点)に総花的に人証尋問等の証拠調べが行われる恐れが大であり,当事者に紛争解決の保証を付与できないし,個別事案の裁判を通じての具体的な法の創造もできない結果を見ることになりかねない。
3 むろん,現状のままの裁判運営でも,多くの簡単な事案は当事者に不満は残っても上記のような問題は生じないであろう。しかし,少し難解な事案となると,その影響は軽視できない。
例えば,医療過誤を理由とする損害賠償請求事案では,中核となる争点は,当該医療行為の違法性すなわち医療行為規範に違反していることである。ここに医療行為規範とは,平均的医師が日常的に行っている医療慣行の水準にとどまるのではなく,臨床医療上,安全で有効な最善の医療行為すなわち医療水準に適合する医療行為を行えとの全法秩序からの命令である。したがって,裁判所は,個別事案の審理においては,当該患者の全身状態に安全で有効に適応する最善の医療行為はいかなる医療であったかに審理を集中し,証拠調べを行い,その結果に基づき医療行為規範を創造し,紛争を解決することが求められる。事実認定,法律論のいずれであれ,法と証拠に基づいて当事者と議論を尽くし,当事者の主張する対立点を積極的に解消していく運営が望ましい審理であるように思う。しかし,このような裁判運営は医療専門部であっても等しく行われているものではない。
4 上記の原因は取り上げれば際限がないであろうが,一つだけ挙げるならば,筆者は,根本は裁判官,弁護士を含めた法曹実務家に上記役割を託された民事裁判を担える人材が不足していることにあるのではないかと考える。その原因はさらに,経済成長への即効的寄与を優先する政策を背景に進められた感のある,彼の平成の司法制度改革に帰着する。すなわち,これにより法曹養成制度が根底から覆され,併せて,法学部が担ってきた基礎法学に関わる法学教育が瓦解し,法学履修者に対する評価も薄れ,法学そして法曹への魅力は急速に失われ,法律実務家の適性を有する人材の多くが司法の分野を見限り,他の分野に去ってしまったのである。
求められる民事裁判を紛争の解決と具体的法創造を実践する国家作用とみると,その責任は重く,裁判官はもとより弁護士にもこれに全力を傾注できる適性ある人材をより多く、かつより多く呼び戻すことが喫緊の重要課題であるのは明らかであろう。もっともこの類の問題は司法に限らず,行政の分野にも当てはまるところであり,わが国は国の将来に関わる幾重もの危機的事態を抱えているようであり,このような状況下で司法制度改革など困難極まることは明らかである。しかし,それでも少しでも早く,司法制度改革にもう一度取り組まなければならないと考える次第である。