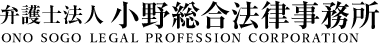2015/07/16 民事訴訟における実体的真実主義及び事実の認定について
代表社員 弁護士 近 藤 基
1 実体的真実主義という概念は、刑事訴訟においてはしばしば用いられその意味も明確である。通常、実体的真実主義には二つの側面、すなわち、犯人は一人たりといえども逃がしてはならないとする積極的実体的真実主義と、無辜の者は一人たりといえども罰してはならないとする消極的実体的真実主義とがあるとされるが、そのいずれにしても、訴訟外に歴史的客観的真実が存在していることを前提として、その真実の探求こそが訴訟の目的とするものである点については争いがない。
しかるに、民事訴訟においては、実体的真実主義という概念はあまりなじみがなく、その意味することは不明確である。その原因は、思うに、民事訴訟で問題になるのは過去の一回限りの不動の事実ではなく常に変転しうる事実であること、民事訴訟で問題となる法律関係は当事者の任意の処分を許すものであること、この二つにあるのではないかと考えられる。そのため、以下で検討するように、民事訴訟の諸原則・諸場面において、実体的真実の探求を必ずしも必要せず、あるいは実体的真実の探求が制約され、さらには実体的真実の探求と背反するように見える場合が生じる。
2 まず処分権主義との関係では、実体的真実に反して請求の放棄・認諾がなされあるいは実体的真実に反する内容の和解が成立した場合にも、これらは有効であり、裁判所はこれに拘束されるという点を指摘できる。また、請求の定立は当事者の専権事項であり、裁判所が当事者の請求の範囲を超えて認容することは、たとえそれが実体的真実に合致する場合でも、許されない。例えば、100万円の貸金の内20万円の返済を受けたので残額の80万円の支払いを求めるという請求に対し、証拠調べの結果100万円の貸借の事実は認定できるが20万円の返済の事実は認定できなかった場合でも、裁判所は80万円の限度でしか認容できない。
3 弁論主義との関係では、当事者が主張しない重要な主要事実をたまたま裁判所が知っていたり、ある主要事実が証拠に現れてはいるが主張には現れてはいない場合、裁判所はその事実を認定できないという形で実体的真実主義が制約を受ける。
4 さらに、実体的真実主義を貫徹すれば判決によって認定された事実は客観的真実ということになるはずだが、もしそうであるならば、判決の相対効ということが説明つかなくなるのではないだろうか。判決が客観的真実であるならば第三者にも判決の効力が及ぶとしてもよさそうだからである。
5 以上のように考えてくると、民事訴訟においては、訴訟を離れた唯一の客観的真実を探求するという意味での実体的真実主義という概念を考えることはできないし、また考える必要もないといえるのではないか。もちろん民事訴訟においても、過去の特定のある事実の存否、例えば保証債務履行請求訴訟で被告が保証をしたか否か(保証書が真正か偽造されたものか)が問題となり、判決でどちらかに認定されることがある(というより、むしろそれが通常である)。しかし、その場合も、認定された事実が客観的真実だったと考える必要はなく、当該訴訟において当該当事者間では、当事者の主張する事実及び当事者の提出する証拠を基礎にする限り、そのように認定できると考えれば必要にして十分である。すなわち、民事訴訟における事実認定とは、以上のようなものであり、それ以上でもそれ以下でもないといえるであろう。そうであるからこそ、第三者がその判決に拘束されないのはもちろん、当該当事者も相手方を異にした別事件では先の判決に反する主張が許されるのである。
上記の考えに対しては、あまりに真実探求の理想を軽視するものであるとする声もあろう。いわば「石が浮かび、木の葉の沈むことが多い」というわけである。しかし、発想を転換すべきであり、むしろ「沈んだものが石であり、浮かんだものが木の葉である」といえるのである。
※司法修習生時代に書いたレポートが出てきました。それの抜粋です。