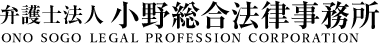2022/08/26 <渉外的離婚問題について>
パートナー 弁護士 湯尻淳也
※小野総合通信 Vol.75(2022年春号・2022年5月1日発行)より転載
1 いつの頃からかは確かな記憶がありませんが、近年の東京家庭裁判所の当事者待合室等には、日本語の案内表示に加えて、外国語の案内が併記されています。そして、実際に、待合室にいる人々を見回すと、明らかに日本人ではない当事者が、驚くほどの割合でいたりすることが多いです。近年の生活環境の急速なグローバル化を背景に、ビジネスなどの問題のみならず、家庭裁判所が取り扱う問題についても、外国人が関係する案件が激増していることを実感します。
2 さて、当事者の一方や双方が外国人である場合の法律問題が日本の裁判所で争われる場合、どのような法律によって規律されているのでしょうか。日本の裁判所で取り扱っているのだから、当然日本の法律が適用されると思われがちですが、必ずしもそうではありません。
この点、ある法律関係について、関連する複数の法律のうち、どの法律を適用するかについては、「法令の適用に関する通則法」という法律が定められています(以下、「通則法」といいます。)。そして、同法律によって指定され、適用される法律を「準拠法」といいます。
3 本稿では、当事者の一方又は双方が外国人である、いわゆる渉外的な離婚問題に関する下記の設例をもとに、どのような法律が適用されるのか見て行きましょう。
(設例)
東京都在住のアメリカ人夫婦(A州出身の夫と、B州出身の妻で、それぞれが成人するまで出身州で生活していた。)で、出生以来日本に居住する未成年者の子が1人いる。
(1) 通則法第25条は、「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による」と規定し、その条文が離婚について準用されています(通則法第27条)ています。
上記の条文を適用すると、共通本国法は「アメリカ法」なので、それに基づいて効力が決せられそうです。しかし、アメリカは州によって異なる法律が制定されている「場所的不統一法国」に該当します。本例のように夫婦の出身州が異なる場合には、単純に本国法が同一とは言えないことになります。
(2) この場合、通則法第38条第3項は、「当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする」との規定があります。
すなわち、アメリカに、その人の本国法を取り決める規則があれば、その規則により指定された法律が共通かどうかで判断されることになります。しかし、複数の下級審裁判例で、アメリカにはそのような規則は存在しないと判断された事例があり、結局のところ、各当事者の「密接関連法」がそれぞれの本国法とされ、本設例では夫につきA州法が、妻につきB州法が本国法とされ、共通本国法は存在しないという結論になるものと考えられます。
そうすると、夫婦は東京都に居住していることから、「共通常居所地法」である日本法が離婚についての準拠法となり、アメリカ人夫婦でありながら、日本の民法に従って、離婚の効力が決せられることになります。
(3) また、未成年者の子については、その親権者の指定が問題となります。この点につき通則法は、「親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による」としています(第32条)。
そうした場合、アメリカ人夫婦の子は、通常はアメリカ国籍であるといえ、あまり問題が生じないようにも思えますが、実際はそうでもありません。設例のように、未成年の子が出生以来日本に居住している場合であっても、両親のいずれかの実家が存在する州には、夏休み等に訪問することが多く、同州法が「密接関連地法」(通則法第38条第3項)とされることが一般的と思われ、その場合は同法を準拠法として親子関係が判断されます。しかしながら、両親のいずれの実家も既に他州に移転し、子は従来の両親の実家が存在した州には訪れたことがないが、現在の実家には複数回訪問しているという事例も考えられます。
このような場合、子の本国法は、両親のいずれかの現在の実家が存在する法律が密接関連地法として指定される場合が多く、その場合、両親のいずれとも本国法が異なることになります。その結果、「子の常居所地法」として、日本法が親子関係の準拠法に指定されることになります。
4 以上のように、渉外的な法律関係にどのような法律が適用されるかについては、当事者の国籍のみならず、様々な事情に左右され、非常に複雑な判断となる場合が多く、法の適用が主たる争点となる事例も少なくありません。また、フィリピン法等はそもそも離婚を認めていませんが、当該法律が準拠法となる場合、日本の裁判所でも離婚を一切認めないとの判断ができるかなど、多くの法律問題があり、今後も問題となる事例は増えこそすれ、減ることはないものと思われます。